編集者の仕事
中道さん:今月の「新着情報」、トップ記事は「新著に向けて」。いよいよ三年ぶりに本を出されるわけですね。楽しみです。
猛志君:僕も同じで、興奮しました。どんな本を書かれるのか、期待があります。
直言先生:まあまあ、お二人とも……。出版の計画は、これから。あまりハッキリしたことは言えない、というように断っているはずですが。
中:新著刊行の決定ではない、という含みをもたされたわけですね。新しい本を出す、と断言されないことに、何か理由があるのでしょうか。
直:出版計画を具体化するためには、いろいろハードルがあって、それをクリアーしなければなりません。お分かりでしょうが、出版を引き受けてくれる会社、とりわけ編集者の存在が、絶対の条件です。長年私とコンビを組んできた敏腕の編集者が、ほとんど引退してしまい、相談できる相手がいない、というのが大きなネックです。
猛:経験のない僕にはよく分からない話ですが、良い本を出すためには、作者と編集者のコンビが重要だという話を聞いたことがあります。
直:本をつくるのは、作者と編集者の協働作業。書きたい作者の思いを理解し、作品を仕上げるために必要なサポートを引き受けることが、編集者の役目。障害者マラソンの伴走者のような存在です。
中:これまで書かれてきた著書や編著は、協力してくれる編集者の支えがあってこそ生まれた、ということですね。協働作業という点で、先生が忘れられないような思い出はおありでしょうか。
直:いっぱいあって、数えきれないぐらいですが、一つだけ。『〈あいだ〉を開く――レンマの地平』(世界思想社)の執筆が進まないうちに、脳卒中で倒れたことはご存じでしょう。退院して書き上げたそのころ、担当者のTさんが定年で退職、若い女性のNさんが後を引き継ぎました。原稿の校正にかかる段階だったと思います。
中:会社でも業務の引継ぎには、メンドウがつきものです。本の編集作業を引き継ぐのも、たいへんだったのではないでしょうか。
直:Nさんは、いろいろ苦労されたと思います。細かい表現のチェックなど、一点一画をゆるがせにしないTさんの姿勢を引き継いだうえ、それよりも厳格な校正の手を入れられたことに驚きました。著者が思いつかないようなサポートをされたこともあります。
猛:何か印象に残っているエピソードはありますか。
直:仏教では、生と死とを切り離すことなく、連続的にとらえる死生観があります、ひとことで「無常観」と言ってもよい。「生きているものは生きていない。だから生きているのだ」という逆説(『金剛般若経』)に関して、「生と死とが場所的に近接している」ように描いた仏画が存在します。たとえば『小野小町九相図』は、絶世の美女小町が、死後、野ざらしのまま朽ち果てて白骨死体となる変化を、九つの相として一枚の画に仕立てています。Nさんは、それを本文中に挿入してはどうか、という提案をされました。
中:で、どうなりましたか。
直:私はOKだと答えましたが、Nさんは止めるという最終判断。あまりにエゲツナイ図柄ですから、当然の判断でしょう。
中:先生のご本にそういう図は入っていません。入っていたら、読者がショックを受けたかもしれません。
直:そういういろんな経緯があって、一冊の本が仕上がりました。著者の存在ばかりクローズアップされますが、優秀な編集者との協力関係が不可欠であることを知っていただきたいと思います。
〈中〉のロゴスとは?
猛:新しい著書のタイトルは、「〈中〉のロゴス」とか。先生がよく使われる「中の論理」ではありません。このテーマにされた理由は、何でしょうか。
直:「ロゴス」は、「論理」と同じ意味の言葉として、よく使われます。ギリシア語「ロゴス」から「ロジック」つまり「論理」が生まれたことからすると、「ロゴス」イコール「論理」と受けとめられたとしても、不思議はない。けれども、「ロゴス」には「論理」以外の意味がある。ご存じですか?
中:『ヨハネ福音書』の出だしは、「はじめにことばがあった」です。たしか、その中の「ことば」が、「ロゴス」だったかと思います。
直:そうです。それなら、次の文も覚えておいでですね。
中:記憶が不確かなもので……神がどうとか、という言い回しでした。
直:「ことばは神とともにあった。ことばは神であった」と続きます。つまり、ロゴスは神の「ことば」、さらには神そのものを指す。私たちが日常用いる意味での「ことば」というより、神がこの世界をつくった筋道、道理を表す「ことば」が、ロゴスなのです。それは、絶対的に正しく、間違いのない考えだから、そういう意味で「論理」ということになるわけです。
猛:それなら、〈中〉の「論理」と言えばよさそうなのに、どうしてわざわざ「ロゴス」という言い方をされるのか、よく分かりません。
直:ロゴスが「ことわり」と訳される場合があることを、君ならご存じでしょう。「ことわり」は、「物事の筋道」を意味する以上、「論理」を含んでいるけれども、論理に限ることなく、もっと広い意味を含んでいます。私があえて〈中〉の「ロゴス」というのも、この語に「ことわり」のような広い意味をもたせたい、という考えがあってのことです。
猛:「ことわり」を表す「ロゴス」を、「論理」よりも広い概念として使う、ということですね。「論理」では表せない〈中〉の意味って、どういうものですか。どうして「中の論理」じゃいけないのか、僕には理由がよく分かりません。
直:簡単にいうなら、「道徳」の問題です。〈中〉は、道徳の理念として重要な意味をもっている。それが〈中〉の「論理」では表せない。そのことを念頭に置いて、「〈中〉のロゴス」をテーマに掲げたわけです。
中:「〈中〉の論理」ではなく「〈中〉のロゴス」が選ばれたのは、道徳の問題だからであると。そのことをくわしく説明していただけないでしょうか。
直:承知しました。この問題を考える手がかりとなった山内得立の『新しい道徳の問題点』(理想社、1958年)を引き合いに出して、私の考えるところを説明しましょう。
講義:〈中〉の道徳
現象学などの現代哲学から出発して、古代・中世哲学を京大で教えた山内得立(1890-1982)の本領は、西洋哲学全般の研究。日本人研究者として一般的なキャリアを積んだ彼が、高齢になってから、東洋思想独自の意義をアピールする『ロゴスとレンマ』(岩波書店、1974年)などを著して、〈東西思想の総合〉へと歩み出したことは、私の著書や論文でご存じの方もおいででしょう。その彼が、戦後復興が落ち着いた時期に発表した『新しい道徳の問題点』(以下、『新しい』)は、論理学や存在論といったテーマを手がけてきた山内が、はじめて世に出した道徳論、異色の著作と言えます。なぜ彼が、この時期にそういう書物を出そうとしたのか。次の一文に、その思いが表れています。
現代の日本に於ける道徳の中心問題は、東洋的なる「忠孝」の思想と西洋の主徳たる「正義」との二つを如何に取扱うべきかということに懸っているのではないか(『新しい』「序」)。
この一文から、どんな印象を受けられるでしょうか。ここに表明されているのは、東洋の「忠孝」と西洋の「正義」とをいかに取り扱うべきか、つまり異なる二つの道徳のどちらを採るか、またはいかに折り合わせるか、という課題です。戦前の天皇中心国家は、封建的なイエ社会。敗戦後の日本は、国民主権の「民主主義」社会。1950年代後半は、戦前と戦後のギャップが、社会的な混乱を露わにしてきた時代であったと言えるでしょう。劇的に変化した国家体制に生じた歪み。その中で当時、京大を退職して京都教育大学長であった山内は、新旧の道徳規範を比較し、国民道徳のあるべき姿を探り当てようとする思いから、あえて道徳論のテーマに踏み込もうとしたのではないかと推察されます。
戦前の封建道徳を過去の遺物であるとして捨て去り、民主主義ないし個人主義のルールに乗り換える。そういうタテマエに、戦後10年以上も経つと、あちこちホコロビが生じてくることは避けられません。日本社会の底流に生きつづける道徳感はそのままで、表層にかぶさった民主主義的理念とのズレが生じてきた場合、そのいずれかを取って他を捨てる、といった選択が不可能であるとすれば、どういう道が考えられるか。山内が選ぼうとしたのは、単に東洋的でもなければ西洋的でもないような第三の道、東西の〈あいだ〉を開く道であった、と言えるように思います。彼が着目したのは、東洋思想にも西洋思想にも存在する〈中〉の道徳、具体的には「中庸」でした――「中庸」は、儒教の中心理念であるとともに、アリストテレス『ニコマコス倫理学』でも、倫理の典型として論じられています。東西世界の古代に「中庸」の理念が成立していたとすれば、それを柱に現代の道徳を立て直そうと考えるのは、もっともだと思われます。
では、「中庸」とはどういうものでしょうか。「中」はさておき、「庚」と「用」からつくられた「庸」には、「もちいる、つねに」の意があり、「凡庸」が示すように、「平凡」であって、それゆえに変わらない一定のあり方を表します。「中庸」は、さしあたり日常の暮らしに必要な心がまえとして、極端なよさではなく、「程々のよさ」ととらえても、大きな間違いはないと思われます。道徳に「最高善」――カントの用語――を求める人からすると、はなはだ物足りなく見えるのが、「中庸」の徳。要は、山内がそういう「中庸」をあるべき道徳の基礎に見立てた事実にあります。それは、どうしてでしょうか。東洋的な「忠孝」と西洋由来の「正義」、先に挙げたこの二つの異質な道徳の共通部分に、「中庸」を位置づけようとする思惑が働いたからです。
四書の一つである『中庸』と古代ギリシアの『ニコマコス倫理学』。東西の両古典をめぐって繰り広げられる詳細な検討は、非常に興味をそそられる内容ですが、ここでは略します。結論的に言えば、二つのテクストに論じられる「中庸」を、山内は〈中〉の論理として認めません。中庸は、道徳の教えとしては有力であっても、そこには哲学に不可欠な「論理」が欠けているという理由で、それを戦後道徳の基礎として位置づけようとする当初の試みは、破棄されてしまうのです。ここには、哲学にとって何より重要なものは「論理」である、という論理至上主義が、顔をのぞかせています。『新しい』よりも16年後に発表された『ロゴスとレンマ』(1974年)の中では、龍樹(ナーガールジュナ)の『中論』から考えつかれたテトラレンマが、「中の論理」として認定され、『新しい』に展開された道徳論は、論理にまで至らぬ「単なる道徳的教説」として、軽くあしらわれてしまいます。道徳の問題から入って、東西共通の「中庸」に注目した彼が、それは道徳であって論理ではない、として当初の着眼点から離れてしまったことは、私にとっては残念という以外にありません。
山内の展開した道徳論に対して、私には共感と疑問とが相半ばします。疑問を二つ提起して、講義を結ぶことにします。一つは、道徳の問題は、哲学的「論理」によってではなく、道徳にふさわしい「ロゴス」によって扱われるべきではないか、ということ。もう一つは、「中庸」が、そういう意味の「〈中〉のロゴス」にふさわしいと認めるべきではないか、ということ。以上、二点です。
二つの疑問点
直:『新しい』という道徳論のテクストから、共感点、疑問点を両方挙げました。お二人の感想を伺いましょう。まずは、中道さんから。
中:山内先生の「レンマの論理」には、先生のご本でなじんできましたが、道徳論については、はじめて伺いました。それに対して、共感と疑問が両方あるとおっしゃいました。すみませんが、共感されるのはどういう点でしょうか。
直:「中庸」という具体的な理念を、東西に共通する道徳の基礎に見立てたことです。〈中〉が道徳の核心である、と見抜いた彼の眼力に敬服します。
中:これまでどおり、山内先生の哲学を高く評価されるわけですね。それでは、疑問点とおっしゃるのは?
直:道徳の根本である〈中〉を、「論理」の土俵に上げて論じようとしたものの、結局それは「論理」ではないとして、土俵の外に追いやったことです。つまり、〈中〉の道徳を狭い意味の「論理」ではなく、広義の「ロゴス」として取り扱わなかったということが、私の第一の疑問点です。
中:そうですか。中の「論理」ではなく、「ロゴス」を問題にされなかった、そのことに不満があるということですね。
直:そういうことです。そのあたりについて、猛志君はいかがですか。
猛:「中の論理」を認めるかどうかについて、僕は前から疑問をもっています。でも、それよりも先に、「忠孝」と「正義」とを比較する、というような問題の立て方に、違和感があります。
直:ほう、それはどうしてですか。
猛:僕の受けてきた学校教育の中で、「忠孝」なんて言葉を耳にしたことは、一回もありません。戦後に発表された本にしては、ずいぶんアナクロの議論だなあ、という印象を受けました。
直:戦前の「修身」から戦後の「道徳」へ、教科書の名称も変わりました。昔なら、当然のものであった「忠孝」の文字が一掃されている現実からすれば、君がアナクロを感じるのも、無理はないかもしれない。
中:先生に年齢の近い私から見ると、『新しい』が書かれた1958年当時、戦後の民主主義体制が定着したようでありながら、戦前に戻ろうとする反動も目に付く。山内先生は、そういう日本社会の情勢を汲んで、あえて道徳論に向かわれたのではないか。そんなふうに感じました。
直:そうですか。かなり共感的な受けとめ方をされていますね。「忠孝」云々については、どう思われますか。
中:「忠孝」は、江戸時代からずっと続いてきた儒教道徳の代名詞です。そんなものは、自分が受けてきた戦後民主主義の教育をつうじて、一掃されたかと思いきや、自分の血肉にしみこんでいる部分があることを、最近になって感じるようになりました。
直:おっしゃったことは、私が日ごろ感じることと同じです。意識の表層にある近代的な市民感覚と、深層にわだかまる共同体的情感とが、ときどき衝突する感じというか、内なるギャップに気づかされることが、しばしばあります。若い猛志君には、解りにくいことかもしれませんが。
猛:お二人の言われる「ギャップ」は、僕にはピンときません。それよりも、「中の論理」と「中のロゴス」との区別について、以前の対話――「風土学の最前線」(1)(2024年11月21日)――を振り返りながら、議論をやり直せたらありがたいのですが、かまいませんか。
直:どうぞ、何でも言ってください。
道徳と論理
猛:講義の中で、「中庸」は「単なる道徳的教説」であって「中の論理」ではない、という山内得立の考えが取り上げられました。よく解らないのは、「道徳」と「論理」とが別のものとして区別されている点です。道徳は論理ではないということが、どうして言えるのでしょうか。
直:非常に重要な問題です。「中庸」が「中の論理」ではない、という山内の主張には、問題があるということを説明しましたが、道徳と論理とのあいだに一線を引くという態度について、私に異論はありません。道徳は論理ではない。この点に関しては、私は山内と同意見です。
猛:どうしてですか。道徳は、「正しい」ことを基本に成り立っています。正と不正とを分ける判断が、もし論理でないとしたら、道徳は何を根拠にするのですか。
直:いかにもカントを専攻する君らしい考えですが、善悪や正不正の道徳的判断は、もちろん論理に関係します。けれども、「中庸」は、そういう論理では扱えない〈中〉に関係するのです。
猛:おっしゃることの意味が理解できません。どういうことですか。
直:君が「正しさ」「正義」の原理と考える「善」そのものと、日常生活の場面に要求される「よさ」とを区別しなければなりません。前者は、プラトンがうちたてた「善のイデア」と、それを継承したカントの「最高善」に代表されるが、それと後者の「よさ」とは異なります。前者は「論理」的に表現されるが、後者である〈中〉の道徳、「中庸」は、論理的には表現できない、というか表現しづらいということです。言っていることの意味は、解りますか。
猛:〈中〉の道徳が、論理的に表現できないというのは、どうしてですか。
直:善と悪、正と不正とを二分するというように、二分法で考えるのが、ロジック(論理)の常だからです。君が二値論理的発想に立つかぎり、排中律が成立します。したがって、〈中〉は論理的に表現することができない、という結論になるわけです。
猛:それに対して、レンマによる「中の論理」が、山内によってうちだされたという話は、何度も繰り返し聞いています。ですが、いまお訊きしているのは、〈中〉の道徳がどう表現されるか、という問題です。〈中〉の道徳を表現する論理はないのですか。
直:あります、〈ロゴス〉の表現としてなら。たとえば、山内がこう述べるように――「中の質的なるものは中(あた)るということである。的中することである。適宜なることである。中は義であり義は宜でなければならない」(『新しい』90頁)。
中:いま引かれた説明の中の「義は宜でなければならない」という言い方が気になります。「宜」というのは、「義」つまり正義の「義」とは異なる意味なのでしょうか。
直:それがポイントです。「宜」とされるのは、絶対的な「善」ではなく、個別的具体的に宜しきもの、適宜なるものです。そういう「よさ」が、「中庸」の徳を表しています。
猛:いま説明されたことは、漢語で書かれた『中庸』の解釈ということなら分かります。アリストテレスの場合にも、それが当てはまるのですか。
直:「宜」に対応するのは、「カイロス」(kairos)というギリシア語。アリストテレスは、「カイロス」を「時宜に適(かな)ったよさ」の意味で用いています。カイロスにかかわる判断力が、「プロネーシス」(思慮)である。ちなみに山内は、『新しい』の中で、「中庸」に続く一章を「プロネーシス」に充てて、くわしい説明を行っています。
中:そういうことなら、山内先生は、「中庸」や「プロネーシス」を「中の論理」として評価されていたように思われます。そうではないのですか。
直:おっしゃるとおりです。私もそう考えたいのですが、山内本人は、「中庸」を「中の論理」としては認めません。その理由は、彼が猛志君と同様、「論理」を西洋哲学の枠組みに沿った「ロジック」として考えていたからです。
猛:でも、『ロゴスとレンマ』では、西洋の「ロゴス的論理」の対極に、東洋の「レンマ的論理」が置かれています。「中庸」はレンマ的「論理」ではないのですか。
直:「レンマの論理」と称されたものは、大乗仏教の祖である龍樹の発想をもとに組み上げられた「テトラレンマ」(四つのレンマ)の形式です。それは、仏教の思考方式をつきつめた形で表現していますが、そこには道徳的な〈中〉は表現されていません。「中庸」つまり〈中〉の道徳は、論理の〈外〉、というと言いすぎですが、論理の〈周辺〉に追いやられてしまった、という印象を受けるのです。
中:とても難しい問題で、私の出る幕はないのですけれども、「中庸」のような道徳を考えるための枠組みを、「論理」よりも緩やかな「ロゴス」に変更されたと。そう受けとっても、よろしいでしょうか。
直:私の言いたいポイントを、うまくフォローしてもらったように思います。
猛:道徳が論理か非論理か、という問題に対して、僕はそれを論理として考えたい。しかし、いま中道さんがおっしゃったような意味で、「ロゴス」を用いるというのであれば、いちおうナットクします。
直:それなら、とりあえず中が「論理」かどうかという問題は、一段落したことにさせてもらいます。先ほど挙げた二つ目の疑問点、「中庸」が「〈中〉のロゴス」にふさわしいかどうか、という問題に移りましょう。
なぜ「中庸」なのか
猛:大きな疑問を挙げさせてください。講義の中で、「中庸」は「善のイデア」や「最高善」とは違って、「程々のよさ」を意味する、というように言われた。それが、どうして普遍的な道徳の基礎とされるのか、まったく理解できません。
直:君の疑問は、もっともです。なんたって、カント的な道徳の理想は最高善ですからね。そういう最高水準の道徳から見たら、「程々のよさ」なんていうのは、とても道徳の基準にならないと思われるでしょうから。
猛:そうおっしゃるのなら、「〈中〉のロゴス」というような発想を取り下げる必要があるのじゃありませんか。「〈最高〉のロゴス」ならまだしも。
直:〈最高〉というのは、現実にはない究極目標として意味がある。言い換えるなら、〈中〉があるからこそ、「最高」があるのです。〈中〉は現実、〈最高〉は理想、この二つの水準を区別しなければ、道徳に関する議論は不毛になる。この点について、どうですか、中道さん?
中:議論への参加をご遠慮したい私に、矛先が向けられましたか。私の名前である「中道」には、〈最高〉の行き方という意味はないと思います。しかし、それでは、「中道」って何だ、なぜそれがよいと言えるのか。そう問いつめられても、説明できないというのが、恥ずかしながら当方の現状です。
直:その答えで十分です。最高・最善であるということが主張できない、まさにそのところに、〈中〉の意義があるのですから。
中:すみません。たぶん私を弁護してくださっているようですが、何をおっしゃっているのか、全然解りません。〈中〉は〈最高〉ではない、だからこそ意義があるというのは、一体どういうことでしょうか。
直:お名前を引き合いに出して、説明します。「中道」は「道に中(あ)たる」、道を外さない行き方を表します。誰もが道を歩んで生きています。人生は道そのもの。この点に、何か異論がありますか。
猛:ありません。けど、そのことと歩んでいる道が正しいかどうかは、別の問題です。
直:他人の人生をはたから見て、正しいとか間違っているとかいう批評をすることなら、できるでしょう。ですが、目の前にある一本道を歩むしかない当人にとって、それを進むことは〈絶対〉です。
猛:〈絶対〉に引っかかります。他の行き方と比べることなしに、〈絶対〉ということができるのでしょうか。
直:他と比較できないから、〈絶対〉なのです。
中:いまのおっしゃり方で、ピンときました。〈中〉と言われるのは、他の何かと比較できないあり方を指すのでしょうか。
直:本質的なポイントをつかまれましたね。そう、〈中〉というのは、他との比較を絶して、それだけで完結するあり方、絶対のあり方を意味します。
中:では、「道に中(あ)たる」ことは、そういう意味の〈絶対〉として認められるということになりますか。
猛:そういう〈絶対〉を認めてしまったのでは、倫理の正当性が根拠づけられないことになるのではないですか。
直:倫理学者からは、当然その批判が出てくるでしょう。メンドウな議論に立ち入るつもりはないけれども、一つだけ言っておきたい。私が〈中〉や「中道」について言っていることは、「倫理の無根拠性」を唱えてはばからない倫理学者と違わない。違うのは、だれもが認めざるをえないような本質的な倫理――「中庸」に代表される道徳――を認めるか、道徳には根拠がない、だから何をしても――たとえば、人を殺しても――とがめることができない、といったアナーキーな主張に行き着くか、という点です。
猛:いま言われたことは、「メタ倫理学」に対する批判に聞こえましたが。
直:そう受けとられてもかまいません。メタ倫理学は、「どうして人を殺してはいけないのか」というような問いを立てて、世間の常識に挑戦する。その種の問いに対して、通常の論理的思考では答えられません。「~だから」といった理由づけを行うことはできない。倫理学者は、倫理の無根拠性をバクロして、仕事をしたつもりになっています。そこから、本当の学問が始まるというのにね。
猛:「本当の学問」って何ですか。教えてください。
直:「論理」を超えた「ロゴス」を明らかにすることです。今回、最初から強調しているとおり。
猛:僕は、哲学であれば「論理」がなければならない、と思います。それを否定したのでは、学問もへったくれもないでしょう。
直:「ロゴス」は「論理」を否定しません。否定するのは、論理がすベてだという考え方、論理至上主義です。そう言っても、なかなか理解してもらえないようだから、日を変えて、また議論することにしましょう。

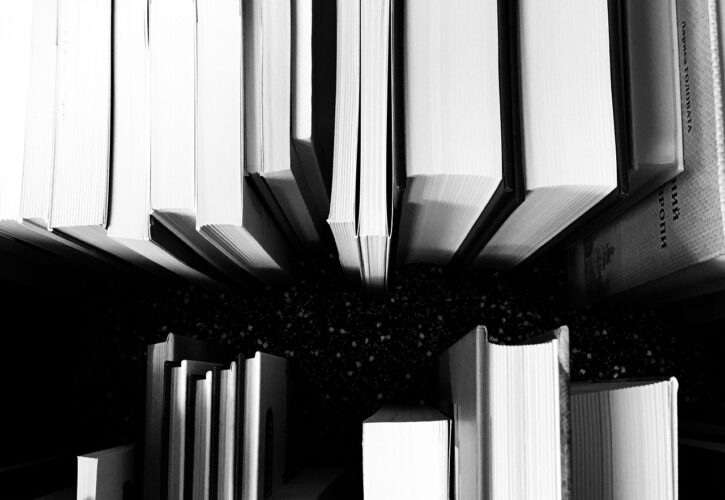

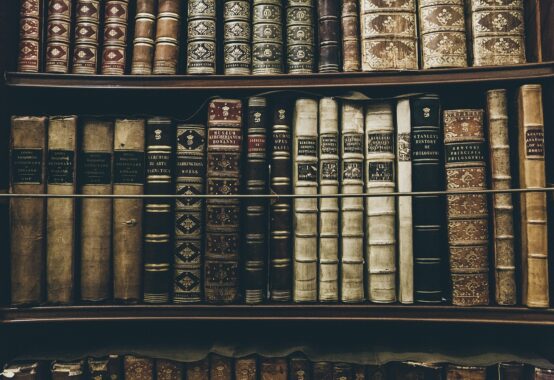


この記事へのコメントはありません。