「弁証法」をめぐって
中道さん:僭越ながら、今回私の方から、前回のおさらいをさせていただきます。『風景の論理』(2007年)よりも前に、1990年代から〈形の論理〉という考えがあったと伺いました。『風景の論理』では、〈形の論理〉を「構造」と「弁証法」によって説明しようとされた。その後、この二つの用語のうち、「弁証法」は使われなくなったということですが、そのあたりの事情を、恐縮ですが、もう一度説明していただけないでしょうか。
直言先生:物事の変化を「矛盾」によって説明するというのが、弁証法の基本です。風景経験の発展変化を説明するには、弁証法が不可欠であると、その当時は考えていました。〈形の論理〉を提唱した三木清と西田幾多郎。この二人がともに弁証法に訴えていたことから、後に続く私も弁証法でなければならない、というようにナイーヴに考えたことが原因です。風景の〈形〉と〈型〉の関係には矛盾はないので、弁証法を用いる必要はないということに、だいぶ経ってから気がつきました。[註。近年は、〈かたち〉〈かた〉のように仮名表記を採用していますが、ここでは当時の流儀で漢字を用います。〈形の論理〉についても同じです。]
中:それは、いつ頃のことですか?
直:10年後の『邂逅の論理』(2017年)の「第七章 形の論理」の註の中で、「弁証法」を用いるのは止めた、と宣言しています。「矛盾」を含まない〈形〉と〈型〉の相関によって、すべてが説明できるという理由からです。
猛志君:戦前の日本では、弁証法が全盛であった。たしか、「弁証法にあらざれば、哲学にあらず」と言われていたということを、前回伺いました。それほど大きな力をもっていた弁証法が、なぜ力を失ったのでしょうか。
直:昭和初期に日本に入ってきた弁証法が、思想界を席巻した大きな理由は、それが左翼のイデオロギー、マルクス主義の理論と一体であったからです。資本家が労働者を搾取する「矛盾」だらけの社会を変えたい、変えなければならないという問題意識が、変革の論理としての弁証法に人々の目を向けさせたわけです。
猛:そういう事情があったことは、分かります。しかし、西田幾多郎や田辺元は、左翼ではありません。左翼でない哲学者が、弁証法にコミットしなければならなかった理由は、どういうものでしょうか。
直:西田の「弁証法的論理」や田辺の「絶対弁証法」というのは、「弁証法」をうたってはいても、同時代に主流であった左翼の弁証法と同じ性格の論理ではありません。あえていうなら、「日本的」弁証法とでも言うべきものです。
猛:いったい何が違うのでしょうか。
直:左翼の弁証法は、唯物論を世界観の基礎にしているので、「唯物弁証法」とか「弁証法的唯物論」と呼ばれます。そういう考え方が正しいと信じる人たちは、西田や田辺のような「ブルジョワ」哲学者の唱える弁証法は、観念論であるというように批判します。
中:唯物論と観念論の違いがあるという訳ですね。先生が「弁証法」の使用を止められたことには、そういう問題があるのですか。
直:いえ全然。日本人哲学者が唱える「弁証法」が、左翼のイデオロギーに一致するかどうかというような問題は、私の眼中にはありませんでした。私が関心をもったのは、西田・田辺をはじめとする日本人哲学者が、本当に言おうとしたことは何なのか、それは「弁証法」では言い表せないような何かではないか、ということでした。
中:もしかすると、その「何か」というのが、〈形の論理〉になるのでしょうか?
直:そうです、そのとおり。弁証法の「論理」では表せない考え方が、日本人の思考にはある。それを弁証法に頼ることなく、自分の言葉で具体化しなければならないということが、『風景の論理』以後、私の中心問題になったわけです。
地理哲学への道
中:そういうことなら、公刊された第二の著書『風土の論理』(2011年)あたりから、〈形の論理〉の新しい展開が生まれたと。そういうことになりますか。
直:『風景の論理』には、「地理哲学への道」という副題を付けています。風土学を「地理哲学」として規定したことは、〈形の論理〉を具体化していくための第一歩であった、ということができます。
中:〈形の論理〉が当てはまるのは、地理哲学においてであると考えられたわけですね。それは、どういうことでしょうか。
直:まず言えるのは、人間存在は、「地理的・空間的」限定を受けるということ。平たく言えば、どういうところに生まれるかで、人間のあり方は変わってくるということです。
猛:それは、和辻哲郎の『風土』や『倫理学』に書かれていることですね。地理哲学は、和辻風土学を土台にして考えられたのでしょうか。
直:風土学と地理哲学とは、私にとってまったくイコールです。『風土の論理』「第一部 歴史的考察篇」は、和辻の手で『風土』が書かれるまでと、『風土』が書かれて以後の風土学の展開とを区切って、歴史的にたどっています。「第二部 理論的考察篇」は、それを承けて、風土学(地理哲学)にとってカギとなる中心概念を取り上げて、その理論を展開しています。
中:他の著書のように〈形の論理〉と題された章が、『風土の論理』には見当たりません。その点からすると、この本では〈形の論理〉というテーマが取り上げられなかったように見えるのですが……
直:たしかにおっしゃるとおり、〈形の論理〉を主題化して論じた章は、『風土の論理』にはありません。しかし、タームとしては表に出なくても、全体の流れは〈形の論理〉を追究する方向をめざしています。
中:どういうことなのか、具体的に説明してくださるよう、お願いします。
講義:風土と〈形の論理〉
2002年のパリ留学前後、とりわけ帰国して以後、『風景の論理』(2007年)を仕上げる過程で、西田や田辺以外にも、戦前(1930年代)の日本人哲学者の思想に、目を向けることが多くなりました。名前を挙げるなら、三木清は当然として、和辻哲郎、九鬼周造、それに山内得立。これらの人々の中には、和辻のように「個と全体の弁証法」を唱えている人もいれば、九鬼のように弁証法を云々することがない人もいるなど、タイプはさまざまですが、共通する一つの傾向が認められる。それは〈形の論理〉である、と同書の中で指摘しています(第四章「四 京都学派と〈形の論理〉」)。
1930年代の日本人哲学者に共通する〈形の論理〉への志向というのは、どういうことでしょうか。それは、人間の生き方、人間性が、地域・空間によってさまざまに異なるという事実への注目です。和辻哲郎が「人間存在の風土性」と呼んだこの事実、そこから考えなければならないという自覚が、ここに名を挙げた人々には見うけられます。和辻自身は、『風土』において「ときとところによって異なる」とした人間存在の構造を、『倫理学』では歴史哲学と風土学によって解明するという方向をとりました。ちなみに田辺元の弁証法は、「種の論理」と名づけられました。それは、人間存在が属する類・種・個の三次元のうち、「種」である国家社会に属するあり方が、人間にとってもっとも基本である、という考えを表しています。そういう考えからすると、異なる「種」に属する主体同士が、どのようにして出会い、理解し合うか、という問題が生じてきます。この問題を「独立なる二元の邂逅」(『偶然性の問題』)と言い表してテーマとしたのが、九鬼周造。九鬼は、〈邂逅の論理〉を問題にした、唯一無二の哲学者です。
日本という〈特殊〉な風土を〈形〉ととらえるなら、世界中の人々は、それぞれの〈形〉をもって生きている。日本の哲学は、西洋から導入されたフィロソフィ(哲学)という一つの〈型〉を学んできたけれども、それと自身の〈形〉との関係を考えなければなりません。日本は、近代化の過程をつうじて欧米列強と向き合い、その行き着く先に西洋近代文明との総力戦を経験しました。日本という〈特殊〉は、他の〈特殊〉と向き合う中で、いかに自己のアイデンティティを確立することができるか。そういう切実な反省が、戦前の激動期を生きる人々のもとに、集中的に生まれてきたと考えられます。そういう意味において、〈形の論理〉は、戦前戦中の日本人が避けて通ることのできない哲学的課題であった、ということができるのです。
では、敗戦という結末によって、日本の近代をめぐる状況はどう変わったでしょうか。変わったともいえるし、変わっていないともいえる。「変わった」というのは、西洋近代との全面対決によって、日本は完膚なきまでに打ちのめされた、という事実。その結果、戦時中に力をもった「日本精神」や「日本主義」の主張など、まったく世界に通用しないという冷厳な事実を突きつけられたことです。それは、近代化をつうじて日本が直面し続けてきた問い――和辻の表現で言えば、「日本とは何か」「日本人とは何ものか」――に、あらためて向き合わなければならない状況が、生まれてきたということです。この問いは、近代化を始めた明治期以来、「変わらない」ものです。敗戦によって、日本の現実は「変わった」。しかし、それによって、明治以来、「変わらない」同じ問いに向き合う事態が生まれてきました。ですから、日本の哲学にとって〈形の論理〉が必要な状況は、戦後も続くのが当然です。
「変わる」と「変わらない」、この二つの区別に引っかけて言うなら、変わるものは〈形〉、変わらないものは〈型〉。問題を〈形〉と〈型〉の関係に移して考えることが可能になる。そう考えるなら、〈形〉と〈型〉の関係を明らかにする〈形の論理〉こそ、日本社会が追究すべきテーマではないか、ということになるわけです。
〈形〉と〈型〉の関係は、最初に「風景」というテーマで具体化されましたが、それを広く風土学全体のテーマとする方針が、2010年前後に固まってきました。『風土の論理』は、この方針に沿って、「風土」の位置づけを「存在論」的に確立しようとした著書です。その狙いは、〈形の論理〉が適用されるフィールドを確定することにありますから、その中で〈形の論理〉自体を主題化することはしませんでした。このころ、〈形の論理〉を推し進めるうえで、きわめて重要なハズミとなった出来事があります。それは、上にも名を挙げた山内得立との出会いです。
『風土の論理』以前と以後とをハッキリ分けることができるのは、山内の哲学から受けたインパクトによってです。西田幾多郎の弟子の中で、最年長に属する山内の哲学的モチーフは、〈東西思想の総合〉です。師である西田には、西洋哲学の受容およびそれとの対決、という課題が明確に自覚されていました。それに続く山内が引き受けようとしたのは、師にはなかった〈総合〉という新たな課題です。〈総合〉は、「融合」や「折衷」とは違うあり方です。この点について一言。西田が禅仏教に深く傾倒し、座禅などをつうじて体得した〈無〉を自身の哲学に取り込んだことは、よく知られています。西田が哲学に取り入れようとしたような意味での〈無〉――よく「絶対無」と表現される――は、彼が学び摂取した西洋哲学の概念にはありません。西洋哲学にとっての土台は、〈無〉ではなく〈有〉、つまり存在であって、非存在としての〈無〉ではありません。〈有〉を根拠とする哲学の論理に、西田は〈無〉を取り入れ、〈無の論理〉と呼ばれる独自のシステムをつくり上げました。それ自体は、たいへんな偉業ですが、それは本来一つにならない要素を混ぜ合わせた折衷の産物、言ってみれば東西思想のチャンポンであって、〈総合〉ではありません。ここで〈総合〉というのは、それぞれ異なる本質をもった西洋と東洋の思想が、たがいに出会うことを意味します。そのさい、〈出会い〉によってそれぞれの個性が失われることはなく、たがいにそれ自体のあり方を維持したまま、一体になったとき、そういうあり方が〈総合〉となります。
山内の代表作である『ロゴスとレンマ』(1974年)は、西洋の論理である「ロゴス」と東洋の論理である「レンマ」とを分け、それぞれの本質を保ったまま共存するような論理体系を構想しました。そういう意味での「東西論理思想の総合」を可能にするカギ、それこそ〈形の論理〉ではないか、という考えにどうにかたどり着いたのが、『風土の論理』を書き上げた2011年前後のことです。そのときから考えてきたことどもは、『〈あいだ〉を開く』(2014年)以後の著書にすべて盛り込まれている、とそれだけ申し上げて、講義は終わりにします。
〈形の論理〉の新展開
直:これまでの講義では取り上げなかったトピックを紹介しました。どういう感想をもたれましたか。
中:〈形の論理〉が、『風土の論理』を世に出された2011年前後から変わってきた、という話の流れでした。その点は理解したつもりですが、肝心の〈形の論理〉の何がどう変わったのかという点については、よくつかめませんでした。
直:お話ししたのは、〈形の論理〉の内容ではなく、それが問題になる文脈です。1930年代の日本人哲学者との出会いをつうじて、なぜ〈形の論理〉を考えなければならないのかという理由が、日本哲学そのものの課題として見えてきた。そういう経緯をお話ししたつもりですが……
猛:いまの講義では、山内得立との出会いが大きな転機であったと語られました。その点に関して、くわしくお訊きしたい疑問があります。
直:望むところです。何でも訊いてください。
猛:一つは、西田と山内との違いについて。先生は、西田哲学をしばしば取り上げて論じていますが、それは西田に対する高い評価を意味していると思います。それなのに、いまのお話では、西田哲学は西洋哲学と対決しながら、それを禅のような東洋思想と〈総合〉しなかった。それに対して、山内は東西思想の〈総合〉を企てたというように、両者の違いが説明された。その違いというのが、どうもよく判りません。
直:そうですか。「判らない」というのは、どういうところですか。
猛:西田の言う「無の論理」は、禅の体験を論理的に表現していると言われています。それって、西洋と東洋の〈総合〉じゃないかと思うのですが、違っているのですか。
直:それは、私の考える〈総合〉とは違います。西田は、「弁証法」という論理の容器に、それとは合わない〈無〉の中身を詰め込んだ。それは、私の理解では、〈折衷〉になります。「チャンポン」という言い方をあえてしたのは、本質の違いを無視することでできあがった作品だからです。
猛:よく分かりませんが、そういうのが〈折衷〉だというのなら、それと〈総合〉とはどこが違うのですか。
直:東西思想の〈総合〉という場合には、西洋の論理と東洋の論理との違いを弁えることが基本です。西洋の考え方を表現する論理形式に、それとは異なる東洋的な思想を当てはめることはしない。東は東、西は西という原則に立って、それぞれの立場の違いをあいまいにしない態度が基本です。
中:「東は東、西は西」という言い方は、たしか西洋の詩人[註.キップリング]にありましたね。その詩の言い方によると、西洋と東洋とは、ついに出会うことがないとのこと。先生のおっしゃる〈出会い〉が、生じないということにならないでしょうか。
直:その疑問は、もっともです。こう考えてみてください。西洋には西洋の論理があり、東洋には東洋の論理がある――山内はこの二つを、「ロゴス」と「レンマ」と呼んで、区別しています。東西の文化が出会ったとき、この二つが異なるということを、それぞれが理解する。西洋と東洋とでは、考えるスタイルとしての論理が同じでないということを、それぞれの主体が認め合う。これが〈出会い〉ということです。「東は東、西は西」ということの相互承認、それが〈出会う〉ということの意味なのです。
中:違っているもの同士が出会うということは、いまのご説明で了解しました。しかし、そういう〈出会い〉が、はたして〈総合〉と呼べるのでしょうか。
直:違ったもの同士が、違いを保ったままで一体になる。それをよしとするかどうかは別にして、弁証法で言われる〈総合〉とは、そういうあり方のことです――定立(テーゼ)と反定立(アンチテーゼ)によって、総合(ジュンテーゼ)が成り立つというように。
猛:そういうことなら、山内が「東西思想の総合」という課題を立てたのは、弁証法につうじていたからだと考えられるのでしょうか。
直:予想していませんでしたが、非常に重要な指摘です。おっしゃるとおり、山内は西洋哲学の本質ともいえる弁証法につうじた、弁証法のスペシャリストです。
猛:先ほど先生は、〈形の論理〉は弁証法ではないという点を強調された。ところが、新たに出会った山内得立は、弁証法のスペシャリストだと。なんだかつじつまが合わない気がします。
直:そうでしょう。同じ「弁証法」と言っても、山内が研究したのは、ふつうにイメージされるヘーゲル・マルクスの弁証法とは違って、古代ギリシアに生まれたプラトン哲学の弁証法です。そういう古代以来の弁証法が、近代に至ってマルクス主義のような形になる。山内がテーマとした古代の弁証法は、〈形の論理〉の展開に大きなヒントを与えてくれました。
中:弁証法に古代と近代の二種類があるという訳ですね。プラトンの弁証法には、どんな特徴があるのでしょうか。そのどこが、〈形の論理〉に関係するのでしょうか。
プラトンの弁証法――二つのもののロゴス
直:「弁証法」は、「ディアレクティク」、ギリシア語の「ディアロゴス」(二つのロゴス)から来た言葉です。「弁証法」と訳されるとチンプンカンプンになりますが、山内の定義は「二つのものの分たれたる区分の間に行はれるところのロゴス」(『體系と展相』「超弁証法」による)。こういう説明なら、どうですか。
中:弁証法は、「二つのものの区分に関するロゴス」であると言い換えられるなら、私のような素人でもなんとかついていけるかな、という気がします。
直:そうでしょう。問題は、その場合の「二つのもの」が何かということです。思いつく二つのものを、何か挙げてください。
中:先生の前にいる猛志君と私、この二人を挙げてもよろしいでしょうか。
直:結構、それを例にしましょう。「ロゴス」は、「言葉」を意味しますが、それを二人の関係を表す言葉としてとらえた場合、何が考えられますか。
中:猛志君と私とは、年齢も立場も違うけれども、ここでは先生と対話をすることのできる間柄、仲間同士の関係です。
直:「仲間同士」というのは、たがいに理解し合える同類を意味します。そう考えて、差し支えありませんか。
中:私はそれで構いませんが、猛志君はどうでしょうか。こちらが仲間だと思っていても、猛志君の方はそう思わないかもしれません。
猛:僕もそう思っています。中道さんと僕は、仲間同士であると。ただときどき、チョット意見が違うな、と思うこともありますけれども。
直:そこが重要なポイントです。仲間同士の関係であっても、ときに意見の相違が生じて、対立することがある。そういう場合、お二人はどうしますか。
猛:僕の方は、自分の考えを口に出して、相手にぶつけるようにします。
直:君のことだから、おそらくそうでしょう。で、中道さんは?
中:年長者である自分の方からは、すぐに自分の考えを口に出すよりも、相手の言い分をよく聞いてから、言葉を返すようにしているつもりですが、違うかな?
直:私の受ける印象も、そんな感じです。確かなことは、そういう仕方で、お二人の言葉のやりとり、ディアロゴス(対話)が成立している、という事実です。
中:そうか、二人で言葉をやりとりするから、〈対話〉なのだと。なるほど、それで〈対話〉の意味がよく分かりました。
直:ディアレクティク(弁証法)の基本は、ディアロゴス(対話)です。問題は、お二人の対話のように、たがいに理解し合える対等の関係が成立しないような場合、二つのものの関係をどう説明したらよいか、ということです。
猛:弁証法では、定立と反定立とがたがいに矛盾する、そこから〈総合〉に至るという説明が、先ほどありました。二つのものが対立し合って、対話が成立しない関係、ということになるでしょうか。
直:うまい!いま君の言ったことが、プラトン以来の弁証法のキモの部分です。プラトンの場合、対立する二つのものが何であるかは、お分かりですね。
猛:もちろん、イデアと感覚的世界の二つです。
アナロギアの論理へ
直:超越的なイデアの世界と人間の生きる現実世界、この二つのものは、まったく異なるものとして別々に存在する。プラトンから影響を受けたカントにも、同じ考えがあることは、君なら当然ご存じでしょう。
猛:叡智界と感性界の二世界論。それを知らないカント研究者はいません。
直:二つの世界が別々に存在するというだけでは、話は終わりません。何が問題になりますか、中道さん。
中:素人考えですが、二つの世界がどのように関係するのかが、問題になると思います。
直:そのとおり。「二つのものの区分にかかわるロゴス」である弁証法は、二つの世界の関係を説明しなければなりません。プラトン哲学を教える立場になった山内得立は、弁証法と向き合って、格闘を演じなければならなくなりました。
猛:その問題は、中世哲学では「普遍と個物」の問題になりますね。
直:アリストテレスから発展した中世哲学では、そういう形になりますが、山内はあくまでもプラトンの弁証法にこだわって考えました。
猛:プラトンの弁証法が、アリストテレスと違う点は何でしょうか。
直:異なる二つのものが、媒介するものなしに、異なりを保ったままで結びつくという関係です。ふつうの弁証法では、対立する二者を媒介する第三項があるけれども、プラトンの弁証法では媒介者がない。そういう考えを、山内は「超弁証法」と呼んでいます。
中:思い切ってお訊ねします。いまのお話を専門的な知識なしに聞いていると、分かったような気になる部分とよく分からない部分とがあります。
直:そうですか。分かる部分というのは、どういうところですか。
中:異なる二つのものが、異なりを保ったままで結びつく、とおっしゃった点です。それを聞いて、ああ〈対話〉のことだな、と合点しました。違っていますか。
直:いいえ、そのとおりです。で、よく分からないと言われるのは?
中:他者同士が対立しているのに、「関係」が成り立つというのは、どうしてだろうかという点です。対立する二者が、媒介するものなしに結びつくと。そう聞くと、何か不思議な感じがします。
直:プラトン哲学の最も重大な本質に、注目されましたね。イデアの世界は、われわれの生きる俗世界とはかかわりのない〈絶対〉の世界。そういう〈絶対〉でありながら、それと正反対の〈相対〉の世界に関係する。考えてみれば、不思議なパラドックス(逆説)というほかありません。
猛:古代哲学についての僕の理解は初心者程度ですが、プラトンとカントの関係には非常に関心があります。いま言われたパラドックスに、プラトン自身は答えを出したのでしょうか。
直:いいえ、出していません。プラトンだけでなく、プラトン以後の哲学者たちも答えていない。というより、答えることができない。そう見るほかありません。
中:山内先生はどうですか。山内得立ほどの人なら、プラトンの弁証法について、納得のいく解釈を提出していてもおかしくないと思います。
直:ええ、おっしゃるとおり、山内はプラトンについての決定的な解釈をうちだした、というか、うちだそうとした。それは、間違いなく言えると思います。
中:どんな解釈でしょうか。
直:プラトンの「超弁証法」は「混合の論理」である、というものです。戦前に発表された『體系と展相』(1937年)に収められた論文に、「超弁証法」「混合の論理」があり、その中で難しい議論が行われています。
中:〈混合〉の意味を、教えていただけないでしょうか。
直:自分自身がよく理解できない問題なので、質問されてうまく説明できる自信はありません。山内本人も、「混合の論理」という解釈がうまくいった、とは考えていないように受けとれる。それほど厄介な問題です。
猛:先生の目から見て、〈混合〉というのはどういうことだと考えられますか。
直:〈混合〉というのは、異質なもの同士が混じり合って、融合することがない状態です。イデアと現実世界のように、本質の異なるもの同士は、融合することはありえないけれども、異なることによって結びつく。そういうパラドクシカルな関係を〈混合〉ということができるのではないでしょうか。
中:山内哲学との出会いによって、〈形の論理〉の新たなステージに入られたと。そのことの意義を、一言お聞かせください。
直:山内は、プラトンの弁証法における「混合の論理」を明らかにしようとしたものの、壁にぶつかった。それは、神(絶対)と人(相対)のあいだに、越えられない隔たりがあるということです。その隔たりを、人間の側から超えるために、「アナロギア」(類比)というものが考えられた。「アナロギアの論理」が〈形の論理〉の一種である、という気づきに至ったことで、自分の視界が開けた気がします。そのあたりのことを、『邂逅の論理』(2017年)で明らかにしました。アナロギアとは何か、それが〈形の論理〉であるとは、どういうことかについては、また別の機会に説明できればと思います。


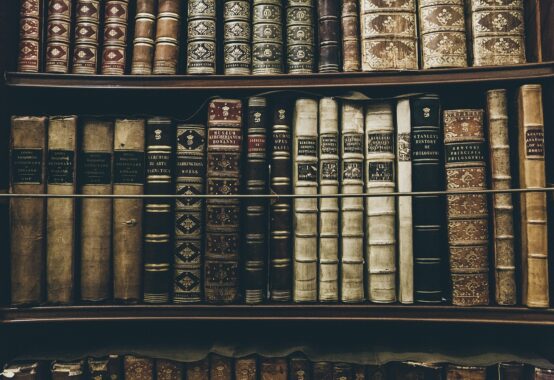

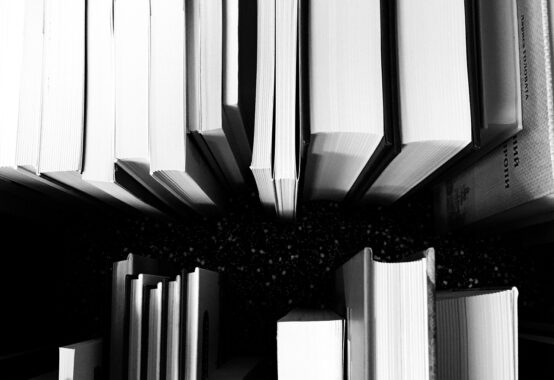

この記事へのコメントはありません。