「下流社会」とは?
直言先生:今日はお二人にお見せするつもりで、本を一冊もってきました。三浦 展(あつし)『下流社会――新たな階層集団の出現』(光文社新書、2005年)。ご存じですか?
中道さん:その本を見るのは初めてですが、著者の名前には憶えがあります。たしか、『ファスト風土化する日本』を書いた社会学者の方ですね?
直:そう、「ファスト風土」とか「下流社会」のように、時流を表す卓抜なネーミングで知られた気鋭の社会学者ですが、大学で教えるのではなく、民間のシンクタンク「カルチャースタディーズ研究所」をつくって、独自の調査活動の成果を世に出しています。
猛志君:「ファスト風土」という表現は、先生の講義で聞いて、面白いキャッチコピーだと思いました。先生は、その方とお知り合いだとか。
直:三浦さんは、ベルク先生からフランスに招かれて、EHESS(フランス国立社会科学高等研究院)で連続講義をされたことがあります。そういうご縁から、先生が日文研で開かれた国際共同研究「日本の住まいと風土性」にも一緒に参加しました。
中:私の記憶する「ファスト風土」は、ロードサイドに大型量販店がずらりと立ち並ぶ郊外の風景などを言い表したものです。そういう風景は、いまも変わらず続いていますが、20年前に造語された「下流社会」についても、同じ状況だということでしょうか。
直:この方の専攻する「郊外社会学」――奥付の著者紹介にある名称――の文脈で言えば、「ファスト風土」は郊外文化の現象面、「下流社会」はそこに生きる人間の意識面を表します。1960年代からの高度経済成長が、都市の肥大による郊外化を生み出すとともに、それまでの国土の風景を一変させ、というより破壊し、かつ人々の意識構造を根本的に変えていったということです。
猛:それを伺うと、『下流社会』に描かれた内容が気になります。どんなことが書かれているのですか。
直:いろんな世代・集団の階層意識の調査結果についての分析です。君は上流・中流・下流という社会階層の区別について、どう考えていますか。
猛:特に意識したことはありませんが、年収一千万円以上なら「中流階級」、一億円以上なら「上流階級」、というぐらいの感じはもっています。
直:まあ、収入の物差しで言ったら、それぐらいの線引きになるかもしれませんね。けれど、この本で言う〈上・中・下〉の区別は、年収のような経済的な指標――それが有意味であることは、間違いないとしても――によるものではなく、社会の中で自分がどの階層に属しているかを自己判定したものです。客観的ではなく、主観的な自己認識の問題ですから、仮に一億円の年収があっても、自分は中流以下の人間だという判断を当人が下したなら、その結果がそのまま統計の数字に表れるわけです。
中:個々人の階層意識を調査するというのは、とてもユニークだと思います。でも、所属する階層を自己判定するというのでは、判断結果が主観的過ぎて、データの信頼性がどうなのかな、と思います。その点については、どう思われますか。
直:階層の上・中・下を客観的に分けることではなく、自分がどの階層にいるかという意識を探ることが調査の目的ですから、結果が主観的であるのは当然です。それよりも、調査対象のサンプリングを分析することによって、どういう結論を引き出すかが重要です。三浦氏は、内閣府による世論調査や自身の主宰する研究所など民間の調査機関が発表したデータをもとに、21世紀初めの日本社会が「下流社会」に向かっている、という結論を引き出しています。
猛:いまの言い方では、客観的にはともかく、主観的に自分が下流に属すると考える人間が増えているということになります。どうして、そうなるのでしょうか。
直:この本で取り上げられる世代は、大きく分ければ、団塊世代・団塊ジュニア世代・新人類世代・昭和ヒトケタ世代の四つ。団塊世代は、昭和20年の敗戦後の数年間、第一次ベビーブームのさなかに生まれた世代――私は、その部類の最後に入ります。この世代が生まれたころの日本社会は、まだ貧しかったものの、昭和ヒトケタやそれ以前の世代の奮闘のおかげで高度経済成長が実現、〈下→中〉への上昇を体験します。そういう団塊世代の子どもに相当する年代の団塊ジュニア世代が生まれた1970年代以降、「一億総中流」と称されるような豊かな社会が到来した。下流から中流への底上げが成立したわけです。
猛:僕が生まれる前の時代のことですから、よく知りませんが、言われていることの意味は分かります。でも、いったん実現したはずの「中流社会」が下流化するとは、いったいどういうことでしょうか。
直:〈上・中・下〉の意識は、固定的ではなく、その時々の社会状況によって相対的に変動するのが当然です。60年代に高嶺の花であったカラーテレビは、その当時は中流のシンボルであったとしても、どの家庭でも手に入るようになって以降は、シンボルの意味を失います。それと同じで、豊かさが進展していくにつれ、現在の水準にとどまることは、相対的意味では〈下降〉していることになります。
猛:つまり、経済成長のペースに合わせて、自分も〈上昇〉しなければ、「中流」の地位は保てないと。そういうことでしょうか。
直:まさにそのとおり。「中流社会」が実現したとして、そこからさらに上をめざすことのできる層と、上昇志向から取り残される層とが分かれる。つまり「格差社会」になるわけです。そういう社会構造において、〈中→上〉ではなく、〈中→下〉という階層意識をもつ人々の割合が増えてくる。これが「下流社会」であると、三浦氏は説明しています。
「中流」が意味するもの
中:いまのお話から、「中流」ならぬ「下流」の社会が何を意味するかが理解できました。社会全体は貧しくないにもかかわらず、自分は〈下〉であると卑下する人が多く生じてくるわけですね。私は「下流社会」という呼び方を、世の中全体の無気力を表すネーミングのように感じました。先生は、どのように受けとめられますか。
直:さすが三浦さんならではの、寸鉄人を刺す表現だと思います。同時に、その言葉が言い表す負の現実は、いま私がなぜ〈中〉の問題にこだわるかを裏づけてくれると考えます。
中:「負の現実」というのは、どういうことを意味するのでしょうか?
直:ひとことで要約するのは難しいけれども、「中流」であることは、ほとんどの者にとって大きな目標としての価値をもっていた。けれども、階層格差が広がる社会では、〈中〉の意味そのものが見失われてしまうということです。
猛:先ほど言われた〈上・中・下〉の区別は、どんな時代でも成立します。豊かになった21世紀の社会にも、それまでの社会と同じく、上流階級・中流階級の区別が成り立つはずです。そうであるなら、〈中〉の意味が失われるなんてことは、ないのじゃありませんか。
直:リクツはそのとおり。高度経済成長によって経済的に底上げされた階層は、「新中間層」と呼ばれます。自民党に対抗する野党、いわゆる「中道」勢力は、この層へのアピールを狙って、税制上の優遇策をうちだそうとしています。
中:国民民主党がこだわる「年収103万円のカベ」突破も、中間層を意識した政策ですね。
直:「教育無償化」もそうですが、財源の問題を二の次にしても、社会の大半を占める中間層に支持されなければ、選挙に勝てないという事情を裏書きしています。
猛:そういうことなら、社会のマジョリティである中流の階層に、〈下〉の意識が広がっているという『下流社会』の説は、少し怪しい気がしてきます。
直:どうしてそう思うのですか。
猛:中間層というのは、現実にはかなり恵まれた社会階層だと思います。その人たちが、いままでよりも豊かな生活をしたいと望むのは、だれにでもある上昇志向だと考えられます。〈中→下〉というような意識ではないように感じます。
直:貧しかった昔に比べて、相対的に豊かになった社会。それを「中流化」として肯定的に受けとめることのできた高度経済成長時代から、「下流化」に意味が一転してしまった、というのが21世紀前半の現実です。
中:先ほど「〈中〉の意味が見失われてしまう」と言われたことが、私には気になります。その点を、わかりやすく説明してください。
二つの〈中〉
直:〈中〉には、大きく二つの意味があります。「中流社会」という場合の「中流」は、「上流」「下流」に対して、そのどちらからも区別される中間、真ん中の状態を言い表します。上・中・下の三区分における「中」、「AとBのあいだ」という場合の「あいだ」も、この意味に重なります。これが、ごく一般的な〈中〉の用法です。それだけなら、〈中〉には価値的な意味はありません。
中:物事の中間的なあり方、ということですね。しかし先生は、私の名前に引っかけて、〈中〉にはそれ自体で「正しい」という意味がある、ということを前におっしゃった。
直:そう、いま言った第一の意味とは違って、〈中〉には物事の正しいあり方、というもう一つの重要な意味があります。それを表すのが、あなたのお名前である「中道」や「中正」「中庸」に含まれる〈中〉なのです。こちらの〈中〉は、それを価値的によいとする肯定的な意味合いがある点で、第一の意味とは異なる特徴があります。先月の対話でお話ししたのは、この意味の〈中〉のことです。
猛:その対話の中で、「中庸」はカントの「最高善」とは違って、「程々のよさ」であると先生が言われた。僕は、それが道徳の基本であるというような先生の考えに対して、納得がいきませんでした。
直:ちょうどよいタイミングなので、その続きをやりましょう。君が、「最高善」に対して「中庸」を評価しない理由は、どこにありますか。
猛:〈中〉は、最高ではないからです。道徳のあり方を追求するなら、程々とか中ぐらいのところではなく、最高の水準をめざすべきだと思います。
直:その言い分は、よく分かります。君以外の研究者や学生のだれに訊いても、同じ答えが返ってくるでしょう。だが、私に言わせれば、だれも〈中〉本来の意味が分かっていない。ここまで考えてきたような〈中〉の第一の意味に引きずられて、本来の第二の意味に気づいていないのです。
中:ここまでのお話では、二つの異なる〈中〉の意味が、どんな風にして分かれるのか、たがいにどう関係するのか、よく分かりません。ご説明をお願いします。
直:前回申し上げたとおり、〈中〉は〈絶対〉を意味する。そういう〈絶対〉があるからこそ、相対的な「中間」という意味が生まれてきた、というのが基本です。この点をハッキリさせるために、山内得立が『新しい道徳の問題点』(1958年)の中で引用している『中庸』の第一章を取り上げて説明します。
講義:「中庸」の地平
『中庸』の第一章には、「喜怒哀楽の未だ発せざる、これを中と謂う。発して皆節に中(あた)る、これを和(か)と謂う。中は天下の大本なり。和は天下の達道なり。中和(ちゅうか)を致して、天地位し、万物育す」とあり、ここに〈中〉の根本思想が述べられています。喜怒哀楽は、人間がもつ四つの対立感情。現実には、そのいずれか一つが人間の感情として発露しますが、それらが「未発」にとどまるときに、それを〈中〉というと記されています。そして、そのうちのいずれか一つが発し、節に中る(しかるべき節度にかなう)とき、それが「和」だとされる。中は万物の偉大な根本であり、和は世界中いつどこでも通用する道である。こうした「中和」によって、宇宙が正しい状態に落ち着き、あらゆるものが健全に生育する、という内容が記されています。山内はこの一節の〈中〉に注目して、〈中〉が〈アタル〉と訓ぜられるとき、「外なる現実に中ること、的中すること適合すること」として、「中和」が成立すると解釈しています。
引用箇所から、山内は、〈中〉には次の三つの意味が区別されるとしています。「一、外に対して内を意味する、二、内外に亘って二つのものの間にあることを意味する、三、二つのものの中ではなくして、何らか一つのものに的中すること。そしておそらくはこの第三の意味が中の最も正しい意味であるであろう」(『新しい道徳の問題点』理想社、1958年、79頁)と。この解釈によって、〈中〉が内と外のように対立する二つのものの〈あいだ〉を意味するとともに、内から発して外の現実に的中するという意味をもつことが判ります。「中庸」など〈中〉の道徳的意味が、主として後者に関係するということも、山内の証言から明らかです。
さらに〈中〉に関して、現実への的中・適合という意味が根本的であることに加えて、二つのものの〈中間〉という意味が生じる次第も、『中庸』のテクストから窺うことができます。未発から既発へ移行し、内なる感情が外に表れたとき、そこに喜怒哀楽のような対立関係に立つ感情のいずれかが成立します。対立する感情のいずれでもない〈中〉というあり方は、対立する二つのもののいずれでもなく、両者の中間であるほかないわけです。「過不及の中」つまり過剰でも過少でもない状態を、それ自体でよしとするのが、「中庸」だと言われます。私の見るところ、それは二項対立のどちらにも属さない中間的位置につくこと、そのことがよいということではなく、その状態が対立以前の〈絶対〉に根ざしていることを意味するのではないでしょうか。
「対立以前の〈絶対〉」という言い方は、他者による批判を受けつけない独善的な態度、というように受けとられかねません。「中庸」が、そういう自己中心的な態度ではないということを、孟子は「誠」という語で言い表しました。「誠は天の道なり、誠ならんとするは人の道なり」という言い方が示すように、「人の道」と「天の道」とが一致するふるまいこそ、〈中〉としての「誠」である、という思想をうちだしたのです。中庸が道徳の教えであるためには、理論の上で「天人相関」――難しい言葉ですが――が前提されなければなりません。言い換えれば、儒教には一種の形而上学が不可欠なのです。山内は、「中庸の説は儒教における唯一の形而上学であり、また論理でもあった」(同書87頁)と記すように、『新しい道徳の問題点』の中で、「中庸」に対する的確な理解と共感を表明しています。
ところが、それから16年後に発表された『ロゴスとレンマ』(1974年)では、この書に記されたような儒教への評価を一変させ、「中庸」は「単なる道徳的教説」である、という否定的な評価が下されてしまいます。道徳から論理が切り離され、「中庸」は、大乗仏教から彼が導き出した「中の論理」よりも下位の「道徳」に位置づけられてしまったのです。この点については、先月の対話「〈中〉の道徳」で説明したことなので、これ以上繰り返しません。
〈中〉の意味は、私たちの生活に息づいています。〈中〉を意識しないでは生きられない、と言ってもよいでしょう。私たちが、当然のように、「下流」ではなく「中流」をめざすのは、〈中〉にもともと目標としての価値があるからです。『中庸』に表現された「現実に的中する」という意味において、〈中〉にはそれ自体でよいとされるあり方が含まれる。けれども、〈中〉には〈上・中・下〉のランクにおける真ん中の意味がある。最上を求める者にとって、それは「中途半端」で不満足な状態である、ということになる。このように異なる二つの〈中〉について、どう考えたらよいでしょうか。
山内得立は、『新しい道徳の問題点』の執筆時点では、中国に発して日本に伝わった「中庸」の徳を、混迷する戦後の社会を導くための指標に掲げようとしたふしがあります。その証拠に、中国や日本だけではなく、古代ギリシアのアリストテレスにも、同じ「中庸」の思想があることを取り上げ、東西の道徳思想の根本に一致点が見られることを強調しています。「中庸」という考えは、東洋と西洋の違いをのりこえ、人類全体に通用する普遍的な価値をもつということが、アピールできるのではないか。山内の書から、そういう期待を抱かされるのです。
そうした期待に反して、『ロゴスとレンマ』では「中庸」に対する評価が取り下げられ、「単なる道徳的教説」として貶められた。道徳と論理の分離、論理の優先によって、彼が具体化した「中の論理」から、〈中〉が本来具えている道徳的意味が切り捨てられた。それによって、〈中〉の本来もつ豊かな意味が、論理的なものに単純化されてしまったのです。
以上、〈中〉の二つの意味のうち、道徳の根本を表す本来の意味に注意を向けていただこうという趣旨の説明を行いました。お二人から質問や意見をいただいて、必要な補足をしたいと考えます。
〈中〉の両義性
中:〈中〉の意味について、私の中では、何となくモヤモヤしたものがあって、割り切れない気持ちが続いていました。いまのお話では、〈中〉には二つの意味があるとして、その違いを明らかにされました。それで、だいぶスッキリしたように感じます。
直:そうですか。「モヤモヤしたもの」をあえて言葉にすると、どういうことになりますか。
中:〈中〉には、「中途半端」のように、あまりよくないもののニュアンスがついて回ります。その一方で、「中流」という言い方には、あこがれの対象のような「よいもの」という意味合いが含まれているように感じられます。〈中〉には、「よい」と「よくない」という両方の価値づけが含まれているようで、もう一つハッキリしない気がするのです。
直:なるほど。〈中〉には肯定と否定、両方のニュアンスがあって、そのどちらともつかないところがある。それを、〈中〉の両義性と言ってもよいでしょう。この点について、猛志君はどうですか。
猛:〈中〉が両義的であるというのは、それが上でもなく下でもない中間であることから生じる、当然の帰結だと思います。善と悪の中間がもしあるとするなら、それは善でもなく悪でもない、それゆえに善でもあり悪でもある。両義性そのものです。
直:ほう、その言い方からすると、山内得立の「即の論理」は、そのまま〈中〉の両義性を意味するわけですね。君は、いまの例のような善悪の〈中間〉を認めますか。
猛:善は善、悪は悪であって、善と悪の中間などはない、というのが僕の意見です。
直:結構。安易に妥協しない君の性格が、その発言によく表れています。もともと哲学という学問の理論に、〈中〉の問題は存在しない。山内先生は、そこに無理やり「中の論理」を持ち込んだわけですが、それは矛盾律や排中律を侵犯せずにはすまない、いわば「反論理」としての論理であった。君が「中の論理」を認めたくないというのは、哲学の学生として無理からぬ立場だと思います。
猛:とおっしゃると、学問の世界に「中の論理」は成り立たないと。先生は、そう認められるわけですね。
直:本日のテーマ「生活から学問へ」にひきつけて、お答えしましょう。「中の論理」は、学問よりも生活にとって重要だというのが、私の考えです。
中:〈中〉が、学問以上に生活にとって重要だとおっしゃるなら、私の実感にしっくりきます。〈中〉の両義性は、哲学では問題にされなくても、われわれがふだんの生活の中でしょっちゅう出会う問題です。
直:中道さんのキャリアからして、そういう意見が出されることは、もっともです。しかしながら、本日のテーマは「生活から学問へ」。〈中〉の意味を生活実感として取り扱うだけにとどまることなく、学問理論に結びつける方向性をうちださなければなりません。
中:意義深いお考えと思われますが、生活から学問へと言われても、具体的な方向性が私には思い浮かびません。
懐徳堂――大坂の学問所
直:「生活から学問へ」というスローガンを実践した江戸時代大坂の学問所、懐徳堂を例に挙げたいと思います。中道さんは、大阪でも仕事をしたことがおありだとか。懐徳堂は、ご存じですか?
中:いや、存じません。大坂の学問所と言われて頭に浮かぶのは、北浜界隈にあったという適塾です。恥ずかしながら、懐徳堂という名前ははじめて伺いました。
直:幕末に緒方洪庵が開いた適塾は、医学など当時最先端の洋学を教えた私塾で、そこから福沢諭吉のような人材が多く育ったことで知られています。それよりも早く、18世紀前半に創建された懐徳堂で教えられたのは、儒学、当時は朱子学が中心でした。
猛:僕の方は、江戸時代の学問史を研究している先生から、懐徳堂の存在を教えられたことがあります。
直:それじゃ、懐徳堂で教えられた学問の内容についても、知識がおありですか。
猛:いえ全然。江戸時代前半にできた学問所ということから、朱子学とか陽明学を教えたのだろう、という程度の見当しかありません。
直:その見当で問題ないのですが、どういう目的で誰に何を教えたか、まではご存じないようですね。
猛:知りません。どういう学問が教えられたのでしょうか。
直:ひとことで言えば、町人が人間らしく生きてゆくための「徳」を、人々の身につけさせるための学問を教えたのです、「懐徳堂」という名称のとおり。
中:大坂の町人と言えば、商人のことですよね。商業をなりわいとする人々に、難しい学問を教えたということでしょうか。
直:そのとおりですが、「難しい学問」という言い方は、必ずしも当たらない。儒学と言っても、『論語』などの古典を厳格に解釈する行き方は、いわば学問のための学問。幕府が認めた学問所の筆頭である江戸の昌平黌(湯島の聖堂)に対して、同じく官許を得た大坂の懐徳堂の方は、民間の町人を相手に、日々の暮らしに活かされる学問を教えた。そこに大きな違いがあります。
中:そうですか、そういう事実があったとは、まったく知りませんでした。それなら、同じ儒学でも、教え方が違うということになるのでしょうね。
直:懐徳堂が最も重んじたのは、四書の中でも『中庸』。その理由は、この書物に明示された「中庸」の道徳こそ、町人に最もふさわしい教えである、という考えがあったことによります。歴代の学主――学長、塾長といった存在――の中でも、第三代の中井竹山とその弟中井履軒は、『中庸』の意義を広く世に伝えたことで有名です。
中:〈中〉の意義について、今回多くのことを教えられました。町人の徳としての「中庸」が、なぜそれほど重視されたのか。ポイントをもう一度、説明していただけないでしょうか。
〈絶対〉としての〈中〉
直:前回、「中庸」が「程々のよさ」を意味するという点で、プラトンの「善のイデア」やカントの「最高善」とは異なるということを述べました。それは、究極の理想を追求する学問理論とは別に、人々の日々の暮らしに必要な心構えとしての「徳」を広めようとしたということです。
猛:そのときも、僕はなぜ最高でなくて〈中〉でなければいけないのかを、先生に質問しました。繰り返しになるけれども、ここでもう一度、同じ質問をさせてください。
直:結構です。その問いに対して、〈中〉がそれ自体〈絶対〉であること、これが一つの答えです。
猛:他とかかわらないあり方が〈絶対〉である。たしか前回、そんなお答えがありました。ですが、それでは、独善的な行き方になるんじゃないか、という反論をしました。
直:〈絶対〉absoluteとは、もともとab-solus「離れて一人在る」ということ。「中道」とは、目の前に開かれた一本の道のようなもので、それを歩むことについて、誰から干渉を受けることもない。そういう意味で、〈絶対〉なのです。
猛:しかし、おのれの行き方を反省することが必要じゃありませんか。つまり、自己を相対化する契機はないのか、ということです。
直:あります、大いに。「中庸」に関して、「過不及の間」に立つこと、過多でも過少でもないあり方をめざす、という考えが強調される。〈中〉について抱かれるふつうのイメージは、そういう意味の〈中間〉というものです。
中:でも先生、おっしゃるとおり「程々のよさ」が成り立つとしても、それでよいのなら、「最高のよさ」など考えなくてもよくなるのではありませんか。これは、私の意見というより、猛志君から提出された疑問です。
直:それに対して、〈中〉があるからこそ〈最高〉が成り立つのだ、という説明をしたことをお忘れですか。「程々のよさ」は、それを最高であるとはしない謙虚さを伴うことによって、はじめて効力をもちます。言い換えるなら、最高の水準があるからこそ、〈中〉が意味をもってきます――〈上〉と〈下〉がなければ、〈中〉がないように。
猛:いま言われたことは、なるほどそうか、とうなずける気がします。けれども、プラトンの場合、「善のイデア」があるから現実世界が成り立つというように、最高の存在がすべてを生み出す原理とされています。〈中〉が絶対だというのは、そういう存在論とは正反対の考えです。それをどう思われますか。
直:よい例を出してくれました。私の考える〈中のロゴス〉は、君が引き合いに出した形而上学の立場とは、真正面から衝突します。学問のための学問ではなく、生活から学問に移行しようとするかぎり、そうならざるをえないのです。このことは、もっとくわしく論じなければなりません。プラトンの場合も含めて、形而上学との対決をさらに推し進めることにしましょう。


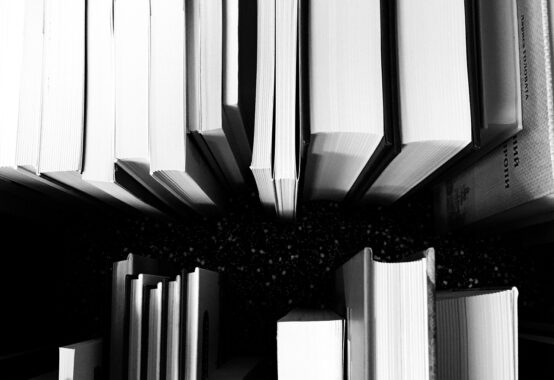

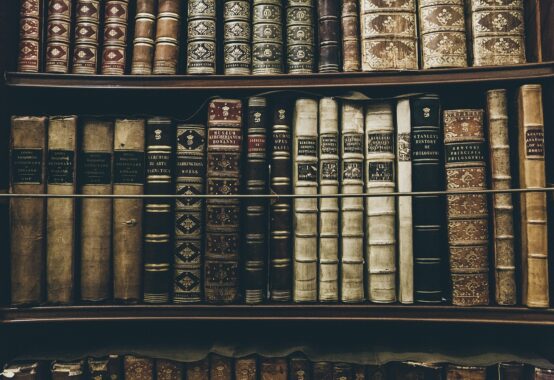

この記事へのコメントはありません。