問題の確認
直言先生:今回は、「欲望と技術」シリーズの3回目。過去2回は、「欲望」と「技術」にそれぞれ焦点化して、いろいろ問題点を考えてきました。そういう流れからすると、これから欲望と技術の関係を追究する流れになると思うのですが、お二人の考えはいかがですか。
猛志君:前回の「技術は何のために」で、技術と欲望の結びつきが、ある程度浮かび上がったような気がします。その続きを議論できたらと思います。
直:そうですか。欲望と技術が結びつくと君が考えたのは、どういうところですか。前回の対話のおさらいをしてください。
猛:何だか試問されているみたいですね。欲望と技術との「結びつき」というのは、技術は「対象の利益のため」、迎合は「技術それ自体のため」というように、プラトンが技術と迎合を区別したことに関係します。医術は、患者という対象に利益をもたらすから、明らかに技術である。でも、料理法はそうではなく、単なる迎合にすぎないということでした。
直:君の言うとおり、『ゴルギアス』で料理法が問題にされたのは、それが対象の利益ではなく、人々の欲望に迎合する、という理由からでしたね。
猛:料理法は技術のように見られているけれども、そうではない。それは、その仕事が、欲望に支配されている、という理由からだと思います。僕の疑問は、たとえそうだとしても、欲望のはたらかない技術なんて、ないのじゃないか、ということです。欲望と結びつかない技術が、あるのかないのか。できれば、そこのところを議論したいと希望します。
直:よく分かりました。中道さんは、いかがですか。
中道さん:すみません。猛志君と違って、私の方は問題の整理ができていません。ただ一つ、先生が最近のAI開発のニュースをどう受けとめていらっしゃるのか、ご意見や感想を伺いたい気がします。
直:最近のニュースと言っても、AIが話題にならない日はないほど、AI関連の問題はひんぱんに取り上げられています。あなたに関心のあるニュースは、どういうものですか。
中:『朝日』の「新世AI」というシリーズが、「変わる戦場 まるで「ゲーム」」という見出しの下に、AIが軍事作戦に利用される現状を取り上げています(3月25日朝刊)。AIの利用を否定しない私でも、ゲーム感覚で人間を殺傷する手段にAIが利用されるのは、間違っていると言わないわけにはいきません。
直:その記事なら、私も読みました。AIを軍事利用することで、対人的な戦闘のように抵抗感を生じることなく、「効率的」に大量殺人が行われる、ということですね。私自身のAI否定論に拍車をかける最悪のニュースですが、中道さんはどうすればよいとお考えですか。
中:『朝日』の第2面を読むと、「自律型致死兵器システム」(LAWS)の開発について、規制に反対するロシア、規制に慎重なイスラエルなど、各国の対応が分かれています。しかし、AI兵器の軍事利用を推進しないという国は、日本を含めてありません。この現実を直視して、AIの軍事利用にストップをかけられるような国際社会のルールづくりが、求められると考えます。
直:おっしゃるとおりですが、AIそのものの規制に積極的なEUでさえ、軍事目的のみの開発・利用を規制の対象外とした現状を見るかぎり、国際的なルールづくりは難しいと思われます。
猛:それじゃあ、どうすればいいのですか。僕の目から見ると、AIの軍事利用は、「戦争に勝ちたい」各国の欲望そのものです。この問題に答えが出せないようなら、このシリーズの意味がなくなると思うのですが。
直:いや、まさに君の言うとおり。しかし、いまの私の立場は、喩えるなら、巨大な風車に立ち向かうドン・キホーテ。ふつうの作戦で現状を変えることは、無理であるということが明らかです。よって、作戦を変更します。
猛:というと?いったい何を標的にされるのですか。
直:本来あるべき技術、技術の正しいあり方、それ自体を表現するということです。それを鏡とすることで、現在のハイテク社会の歪みが映し出されることを期して。先日、武道の世界に出会ったことで、自分のめざすべきこちらの方向が、ハッキリ開かれてきました。
中:とおっしゃるのは、そういう方向が、先月の「新着情報」で取り上げられた「古くて新しい世界」との出会いから生まれた、ということでしょうか。
直:そうです。武道がわれわれに示唆するのは、技術が堕落することなく着実に発展した場合には、〈道の文化〉を生み出す、という厳然たる事実です。そのことを、お二人相手に語りたいと考えます。
中:とても興味深いお話ですが、武道は「欲望の論理」とは関係がないのではないでしょうか。「欲望と技術」のテーマに関係する点があるのか、気になります。
直:ご心配には及びません。武道に含まれる「武」には、元々「生存のための欲求」である戦闘の意味が含まれています。そこから出発した戦いの技術が、最後に「武道」という文化に落ち着く。そういう歴史のプロセスを追うことによって、「欲望を飼いならす」ための適切なモデルが具体化される。そういう事の次第に、最近になって気がついたのです。お二人との対話に入る前に、まず私が気づいたことの要点をお話しします。
講義:武道の成立
先月の「新着情報」で取り上げた「古くて新しい世界」では、私にとって昔からなじみがありながら、忘れていた武道との思いがけない再会――〈邂逅〉と言いたいような――について、その一端を綴りました。ただ、記事の性格上、そこで生じた〈出会い〉による重要な気づきにふれることは、ほとんどできませんでした。そうした気づきのうち、いまどうしてもふれないわけにいかない一点を、ここで取り上げることにします。それは、武道が本来もつ「武術性」に関係します。
「武術性」――聞きなれない言葉ですが、「武道」として確立される以前の「武技」「武術」と言い表されるような「武」の本質を意味します(以下の説明は、志々田文明・大保木輝雄編著『日本武道の武術性とは何か』青弓社、2020年、によります)。戦場において相手と闘うための技術が、武術。武術には、敵を打倒するという本来の目的があり、戦闘の場でのはたらき(技)という実用性がある。それが「武術性」と呼ばれるものです。そういう言葉が注目される背景には、実戦のない近代社会に入り、「武道」がスポーツ競技の一種に組み込まれてしまった現時点で、その技術としての原点を見直すという理由があります。
武術の本質とは何か。敵を攻撃し殺傷する技術である。しかし、その意味を考えるには、数百万年にわたる人類の歴史を通覧しなければならない、というのが編者の考えです。編者の一人志々田氏は、ユヴァル・ノア・ハラリ『サピエンス全史』(河出書房新社、2016年)などの人類史的知見を引いて、現在のヒト(サピエンス)が、多数の生物種やホモ属の他の人類(ネアンデルタール人など)を絶滅させながら、地球上の覇権を握ってゆく歴史を概観しています。集団での狩猟、特に大型獣との闘いでは、敵を倒すための道具とその用法が工夫され、戦闘の技術がしだいに開発されてゆきます。これが武術の原点である、という客観的認識に立って、武道の「武術性」とは何かという問題に答えていくわけです。
今日に至る人類史の大半は、文字どおり武力行使に明け暮れる戦闘の連続。日本に限ってみれば、血なまぐさい戦国乱世が終わって、戦争がない「平和」が成立したのは、江戸時代、高々400年前にすぎません。ちなみに有史以来、「平和」がマクラ言葉になるような時代は、ローマ帝国の五賢帝時代(パックス・ロマーナ、約200年)と日本の徳川時代(約250年)、この二つしかないことを想い起こすなら、平和ではなく戦争が人間社会の常態である、という事実に向き合わざるをえません。つまり、戦闘に用いられる武術が、社会にとって必要不可欠な技術である状況が、歴史をつうじてずっとつづいてきたわけです。ところが、江戸幕府が開かれるや、武士の支配する世の中でありながら、武術の置かれる状況が一変する。戦国時代までのように、敵と相まみえてこれを倒す、といった戦闘があまり行われなくなる。平たく言えば、武術が不要になる。しかし、だからといって、武術自体が消滅するわけではありません。それまでの武術から武芸へ、さらに武道へと変化することで、武の伝統が後世につづいていく礎が築かれる。この転換の意味が、テクストで解き明かされるのです。
数ある武道の中で、剣道に焦点化した論文の一つ、大保木輝雄「剣道の武術性を問う」のサワリをご紹介します。徳川家康は、自ら望んだ平和な時代の到来に当たって、武術の伝統を活かす方向を選びました。それは、治安維持のための武力を確保する必要とは別に、武家社会を支える武士の心身を鍛えるシステムを整備しようと考えたからです。つまり、武術の伝統にもとづく「武士道」のエートスを、確立しようとしたわけです。そのことから、剣術は武士となるための修養の中核に取り込まれます。それまで無数にあった剣術諸流派の中で、他の武術から独立した剣道として再編されるだけの理論性をもつ流派に、幕府のお墨付きが与えられます。「徳川家のお家流になった柳生新陰流や小野派一刀流の流祖は、戦場での実戦的な技術に加えて武士の矜持として身を捨てて大義に生きる勇者を象徴する剣術独自の「究極の一刀」を求める技芸として総合武術からの独立化を図った」(同書62頁)。戦国時代以来の剣術は、身体技法としての柔術などと一体の「総合武術」でした。ここに引かれた柳生新陰流は、元々の剣術の要素を中心として、そこに禅などから心身の鍛錬に不可欠な「心法」を取り入れることで、政治の世界にも応用されるような高次の兵法に変容しました――この変化を実現した柳生但馬守宗矩と禅僧沢庵との交流などは、時代劇によく出てくるので、ご存じの方も多いでしょう。
剣道史は、筆者大保木氏の言葉を借りるなら、時代順に実戦文化・芸道文化・競技文化という流れを構成します。読んでいて興味の尽きない剣道史の詳細に立ち入る余裕は、残念ながらありません。ここで最後に述べたいのは、剣術が剣道に変容していく過程は、技術というものが辿るべきコースを表す絶好の例ではないか、ということです。もともと生きるための欲望に根ざしながら、殺戮の手段という原初的な性格をしだいに払拭して、文化的な武道へと昇華されていく武術。そのように「術」から「道」へと変容する過程を、私は〈道の文化〉の特色に挙げたいと考えます。脈々と生きる「道」の伝統を、それと対極的なハイテク・ブームの世の中において、再興しなければならないと申し上げます。
武道が目ざすもの
猛:武道の種目は、現在、中学校のカリキュラムで正課になっています。僕の場合、柔道か剣道かという選択肢の中で、剣道を選びました。いまの話でおもしろかったのは、剣術と剣道とが違うというところ、戦国の世が終わって、剣術から剣道への変化が起こった、というあたりの話です。
直:そうですか。君がおもしろいと思ったのは、具体的に言うとどういう点ですか。
猛:中学校の剣道の先生は、お年寄りでしたが、いつも「心」のもち方が大事である、というような訓話をされていました。そのころは、剣道ってどうせチャンバラの勝負じゃないか、ぐらいに感じていたことの正体が、いまの講義で何となく分かったような気がします。
直:時代劇のチャンバラでは、人を斬るシーンがしょっちゅう出てきます。人斬りの技術が剣術だと思われたとしても、不思議はない。けれども、江戸時代に求められたのは、殺人のための技術ではなく、勝負をつうじて心身を鍛え上げるシステム、人格修養のための剣道です。
猛:チョットよく分からないのは、勝ちたいと思って、勝つための技術を身に着けるはずなのに、その目的が人格修養だということ。それって、目的のすり替えじゃないのですか。
中:お二人のやりとりを伺っているうちに、昔のことを思い出しました。私も中学校に入ったころ、柔道を少しかじりました。当時、『姿三四郎』や『柔』などのテレビ・ドラマが放映されていて、それに影響を受けたことから、自分も柔道をやってみようという気になりました。
直:それじゃ、美空ひばりが歌った『柔』の主題歌もご存じですね。「勝つと思うな、思えば負けよ~」で始まる――。
中:もちろん、よく覚えています。柔道では、技の習得と同時に精神修養が求められるということ。それも含めて、中学生の私に柔の道へのあこがれが生じたのではないかと思います。
直:明治期に入って、それまであった無数の柔術諸流派を統合して、精神修養の性格をもつ「柔道」を仕上げた功労者が、嘉納治五郎です。『柔』の中では、「矢野正五郎」という名の師範として登場していました。
中:『柔』だったか『姿三四郎』だったか、どちらかでいまでもよく覚えているのは、三四郎が、先生から禁じられている他流試合をしたことで、師から松の木に縛り付けられて泣く場面です。それを見て、闘わないことにこそ修業の意義がある、という精神的な部分にしびれました。
直:敵と闘うために開発された柔術が、闘わないという自己矛盾を引き受けることによって、「柔道」へと変容したことを物語る、象徴的な場面です。猛志君、言っていることの意味がお分かりですか。
猛:おっしゃることは、なるほどと思います。でも、オリンピックなどの国際試合を観ていると、柔の精神なんてことは、ウソ臭い話に聞こえてしまいます。
直:ポイントを稼いで勝つためのスキルが重視されるいまの柔道を観ていると、君の感じる不満がよく理解できる。ところで君は、嘉納治五郎が近代柔道を完成させたと同時に、柔道の国際化への道を切り拓いた先駆者だという事実を知っていますか。
猛:大河ドラマ『蒼天を衝く』に、嘉納治五郎が登場していたので、そんな運動をしていたという事実は知っています。
直:それなら、柔道の国際化の動きの中で、近代スポーツの種目として柔道を国際的に認めさせるために、「一本」ではなくポイントによって勝敗を決する、という方式を受け容れて、妥協せざるをえなかった事情も分かるでしょう。
「一本」の意味
中:先生がおっしゃるのは、「一本」を決めてこそ柔道である、ということですね。私が、ふつうのスポーツではなく柔道にあると思ったのは、一本を取るか取られるか、というハッキリした勝ち負けの世界です。先生は、「一本」について、どう考えられますか。
直:先日の国際武道大学でのディスカッションで、一番大きなインパクトを感じたのが、その問題です。3月6日の午後のセッションで、私は「レンマと武道」という発表を行いました(原稿は、3.21更新「新着情報」に掲載)。その後のディスカッションの中で、日本武道学会会長の大保木先生は、参加者一同を見渡しながら、この中に「見事一本!」を決めたことのある人はいませんか、という問いかけを発せられました。参加者は、国際武道大のスタッフで、もちろん武道家ばかり。当然のこととして、「覚えあり」という人が何人も出てきます――なかには「一本」を決められた経験がある人もいました。そうしたやりとりを拝見しているうちに、ああ、武道の本質は「一本」を取ることにあるんだな、という実感が湧いてきました。まったく思いもかけない出来事でした。
猛:へー、でも柔道の試合では、「一本」が決まれば、それで終わり。「技あり」なら二つで一本に数えられる。ほかに「有効」や「反則」も、勝負を分けるポイントとして評価されます。勝ち負けに関して、一本とそれ以外のポイントに、本質的な違いがあるのでしょうか。
直:あります。柔道や剣道の世界において、「一本」とそうでない技とを差別化することには、武道の武道たる本領がかかっているからです。
中:その点に、私はものすごく興味があります。柔道や剣道が「一本」の世界であるというのは、どういうことかを説明していただけないでしょうか。
直:大保木先生は、「剣道での「見事な一本」が繰り出されると、身体に不思議な快感が走り、その記憶は身体に刻み込まれる」(前掲書90頁)と書かれています。その快感は、武道以外のスポーツにも共通するとされ、自分と相手との関係性の上に成立することを指摘されています。
中:相手との関係性というのは、武道以外のスポーツにも当てはまりますね。何か例が考えられるでしょうか。
直:フロアーと大保木先生とのやりとりの際に、挙手された方がいます。その方は、ラグビーの専門家として、長年競技に携わってきたご自分の経験から、見事にタックルが決まった瞬間、それを決めた方も決められた方も「痛くない」という事実を挙げられ、これぞ「見事一本!」の例ではないか、と問いかけられました。
中:そうですか。で、先生はそれに同意されましたか。
直:もちろんです。それどころか、「レンマと武道」には直接関係のないテーマに連想が働いて、思わずそれを口に出したりしました。自分にとって「閃き」と言えるような、非常に大きな気づきが生じたわけです。
猛:それはどういう閃きですか。聞かせてください。
直:こう言って、はたして通じるかどうか――「一本」が、「善のイデア」に一致するような出来事ではないか、という直感です。
中:武道の「一本」から、プラトンのイデア論を連想されたとは、驚きです。それがどういうことなのか、こちらにも解るように説明していただけますか。
直:私の発表が、〈かたちの論理〉を武道に適用する内容であったことから、そういう連想が自然に働いたように思います。柔道や剣道の試合で選手が繰り出す技は、私の言葉で言うと、さまざまな〈かたち〉、そんなにスパッとは決まりません。ところが、ごくたまに大技が決まって、一本が取れる場合がある。それは、追求してきた〈かたち〉が、〈かた〉に一致した稀有の瞬間だと言えるのではないか、というふうに閃いたわけです。
中:なるほど、いまおっしゃった〈かた〉が、「善のイデア」に相当すると。そう考えられたということですね。
直:そのとおり。ご承知のように、プラトンの二元論では、イデアと感覚的現実とは、たがいに根本的に隔てられているために、双方が一致するということはありえない。ところが、武道では修業の過程をつうじて、そうめったには起こらなくても、たまにおのれの技、つまり〈かたち〉が、理想とする〈かた〉に一致すると感じられる幸福な一瞬がある。それは、西洋でハッキリ分けられている超感覚的な次元(叡智界)と感覚的現実(感性界)とが、双方の隔たりを超えて重なり合うような瞬間です。
猛:「一本」に、二元論を乗り越える秘密があるということですね。でも、一本が決まった後はどうなるのですか。
直:その瞬間において、〈かたち〉は〈かた〉に一致するとしても、それはほんの一瞬でしかない。その後は、稽古であれ試合であれ、これまでと同じ鍛錬や修養の日々がつづくことになります。それが、〈道〉と呼ばれる終わりなき修業の過程の特徴なのです。
〈型〉と〈道〉
中:先生はいま、私が昔あこがれていた柔道の本質にふれるお話をされたと思います。柔の道は、はてしない修業の道である。そういう意味の言葉が、ドラマの中でよく語られていたことを思い出します。
直:日本的な〈道の文化〉は、地平線の彼方に消えていく道のように、はてしなく修業が続けられるというところに、特色があります。昨年書いた論文「〈道のロゴス〉試論」(「研究実績」のページに収録)の中で、そういう認識を表明しています。
中:すみません、論文の抜き刷りを頂戴しながら、いまおっしゃった点には注意していませんでした。論文の中では、〈かたち〉と〈かた〉の関係が論じられていたように記憶するのですが……
直:そのとおり。道がどこまでも続いてゆくように、目標である〈かた〉をめざす修業の過程は、はてしなく続けられる。旅人の目の前に蜃気楼が現れるように、〈かた〉(型)は到達不可能な目標点として意義をもつ。そういう理解を文章にしました。
中:先生の考えられる〈道〉において、〈かたち〉がそのまま〈かた〉に一致することはありえない、というように私は理解しましたが、間違っているでしょうか。
直:いいえ、全然。はてしなく続く道の終わりに到達できないように、修業の実践つまり〈かたち〉の反復は、究極的な〈かた〉には到達できません。つまり原理上、〈かたち〉が〈かた〉に一致することはありえないのです。
中:それでも、先ほど言われた「見事一本」の例は、〈かたち〉が〈かた〉と一致した瞬間だということですね。
直:ええ、ただし「一致した」というのは正確ではなく、「一致したかのごとき」瞬間である、と言い換えなければなりません。
中:それは、どうしてですか。「一致した」と言ってはいけない理由が、何かあるのでしょうか。
直:もしそのとき、〈かたち〉が〈かた〉に一致したなら、その時点で目標を達成したことになり、修業は終わってしまいます。
中:おっしゃる意味は、道がどこまでも続くように、修業が続けられなくてはならない。そのためには、「一本」で〈かた〉が極められてしまってはいけない。そういうことですね。
直:そのとおりです。「見事一本」が決まったということは、〈かたち〉が〈かた〉と一瞬一致したかのような、明確な手ごたえを生み出す。けれども、それは「暫定的一致」にすぎないと承知して、次のステップに向かうというのが、求道の決まりです。
猛:僕は、「一本」が「善のイデア」との一致である、というさっきのお話から、プラトンが区別したイデアと現実との壁が乗り越えられたのか、というふうに感じました。そうとっては、いけないのですか。
直:そうとってもらっても、かまいません。ただ、文字どおり「壁が乗り越えられた」と表現するわけにはいかない事情があることに、注意してください。イデアと現実とは、明確に区別されるし、区別されなければならない。けれども、その区別がありながら、一瞬でも壁が乗り越えられたと感じられる体験が、実際に生じる。その体験を、〈かたち〉が〈かた〉に一致したというのではなく、一致した「かのごとき」瞬間である、と言わなければならない。それが、武道における「見事一本」の意味だということを、申し上げているのです。お分かりになりましたか。
猛:まだよく分からないけど、イデアと現実世界とが、文字どおり「一致した」というわけにはいかない事情を、先生が重視されていることだけは理解しました。
二元論と〈かたちの論理〉
直:それを認めてもらえただけで、私としては十分です。同じ点について、中道さんはいかがですか。
中:猛志君よりもよく分かった、というだけの自信はありませんが、先生は二元論に代るものとして、〈かたちの論理〉を考えておられる。ただいまの点は、その違いに関係するいちばん重要なポイントではないかな、という気がします。
直:そう、よくおっしゃってくださった。二元論にはなくて、〈かたちの論理〉にはあるもの、それが〈理想〉(かた)と〈現実〉(かたち)との暫定的一致、という考えです。二元論では、切り離されたまま接点が見つからない二つの次元。その二つの次元の〈あいだ〉が開かれる、というのが〈かたちの論理〉だということです。
猛:二元論が閉ざした〈あいだ〉を開くということが、先生の風土学のスローガンになっています。二元論と〈かたちの論理〉との違いを、もう一度、僕たちにも解るように説明していただけませんか。
直:承知しました。今回取り上げた武道に沿って、おさらいすることにしましょう。技術であるかぎりの武術・武芸は、いかに効率的に敵を打倒するかを目的として工夫を重ね、各流各派の〈型〉を考え出した。その〈型〉には、二つの意味がある。一つは、それに従って鍛錬することで、技が上達するような「お手本」。もう一つは、個々の〈形〉をどれだけ重ねて行っても、そこには到達しないような究極の目標、プラトンで言えば「善のイデア」のような理想です。あらゆる出来事や行為を生み出す原理とされるイデアそれ自体は、人間がどんなに努力してもつかむことができない。天上のイデアと地上の出来事には、接点がない。これが、古代以来の二元論のアポリア(解決不可能な難問)というものです。しかし、〈道の文化〉を代表する武道の世界では、二元論が切り離して扱う二つの次元が、〈かた〉と〈かたち〉との関係として、修業の過程で具体的に結びつけられる。これまで著書などで論じてきたように、〈かた〉から〈かたち〉が生まれ、〈かたち〉が〈かた〉に収斂する、そういう双方向の運動が成立するのです。そのような〈かたちの論理〉によって、二つの次元を分断する二元論の限界が突破される。そういうことは、これまでも再三主張してきましたが、このたびの武道との〈出会い〉をつうじて、「一本」の意義が、求道(修行)の過程で生じる〈かたち〉と〈かた〉とのかりそめの一致であることを、教えられたという気がします。この発見によって、非二元論――反二元論ではありません――としての〈かたちの論理〉が、よりクリアーに説明できると考えます。
中:よく解りました。新しい著書で、そのことを証明してくださるようお願いします。




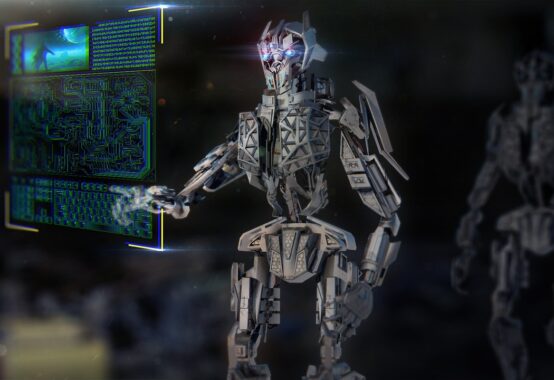

この記事へのコメントはありません。